- Home
- メンタルヘルス 心の症状
- マインドフルネスとの向き合い方
マインドフルネスとの向き合い方
- 2019/1/24
- メンタルヘルス 心の症状
- コメントを書く

「マインドフルネス」という言葉にあなたはどのようなイメージを持っていますか?「マインドフルネス」でネット検索するとたくさんのまとめサイトが上位に表示されていて、様々な効果ややり方の例が掲載されています。そんな中から自分に必要な情報を取り出すのはたいへんかもしれませんね。
| マインドフルネスをどう捉えていますか | マインドフルネスの語源 | 心のモードを変える | 機関紙マインドフルネス研究 |
マインドフルネスをどう捉えていますか

私のところにも「マインドフルネスのトレーニングを受けたい」、「マインドフルネスについて知りたい」というお問い合わせが、様々な方からあります。テレビや雑誌で取り上げられることも多く、書籍などもたくさん出版されているので、関心を持たれる方が増え、一般的に「マインドフルネス」が広く知られるようになったのだと思います。また、心理学、脳科学、仏教などそれぞれの専門家が「マインドフルネス」を探求、理論と実践を繰り返していますが、それぞれの立場から語られるマインドフルネスの定義も一定でなく、共通理解はなかなか難しいとも言われています。
ある食事会の折に、二人の経営者から「マインドフルネスというのが流行っているようだが、どんなものか教えて欲しい。日頃、周囲から強いストレスを感じているので、何か対処になるかもしれない。」というお問い合わせをいただきました。
私は、今までに「マインドフルネスは単なる注意訓練ではない、自分に、他人に温かさを持って行うもの」というご指導をいただいていますので、こころのあり方を変えていくという立場から、次のようにお答えしました。
「慈悲の心を手に入れ、自分にも、他人へも温かな気持ちを向けられるようになり、社会としっかりと繋がっていくためのトレーニングができます。」
その答えにお二人はすっかり興味を失った様子で、失笑しながら、
「慈悲って自分たちとは無縁なものだね。人がどうなろうと興味はないし、まぁ、きっと自分たちには向いていないことなのだろうね。」
と、次の話題に移られていました。このお二人はとても良い方々なのですが、目の前のことで精一杯、うまくいかないことを常に他責にしていることで、自らストレスを感じやすい状態になっているようでした。自分のあり方がストレス原因となっていることに気づいていないのです。このような生き方はさぞお辛いでしょうから、折に触れ、あり方を変える必要性についてお伝えしていこうとこの時は思いました。
また、「慈悲(コンパッション)」についての拒否感については伊藤義徳先生も論文の中で、次のように述べられています。
“マインドフルネスと同様に,セルフコンパッションも体験してみなければその意義は容易に理解しがたい。「慈悲」という言葉だけを聞いて,自分自身の価値観と異なると早合点し拒否反応を示す人も多いかも知れない。“1)
事例を通じてマインドフルネスの一つの側面をお伝えしましたが、皆さんがマインドフルネスに期待すること、目的はどのようなものでしょうか。テレビや雑誌などで取り上げる際は放送や紙面の都合上、部分的であったり、探求の方向を示さずやり方のみ伝えていくような場合もあるかと思います。
急速なマインドフルネスの拡大に対し、日本マインドフルネス学会の第2回大会(平成27年)ではテーマが「マインドフルネスの効果とそのメカニズム」と設定され、専門家の議論を深め、共通理解を見出す取り組みがなされました。また、同第3回大会(平成28年)において大会⻑ 熊野宏昭先生(早稲田大学人間科学学術院教授)は大会長挨拶で次のように述べています。
“ここ1〜2 年、マインドフルネスは、テレビや新聞などでも広く取り上げられ、一部ビジネス化した「あやしい」ものも見受けられるようになっています。この分野の健全な発展のためには、理論と技法、研究と実践を車の両輪として、バランスよく取り組んで行くことが必要です。” 2)
マインドフルネストレーニングを始められる際は、そのトレーニングの理論と技法、研究と実践がしっかりしているかをぜひ、確認しながら行っていただければと思います。また、指導を受ける際には指導者が実践者かどうかも重要なポイントになってきます。専門家の越川房子先生は日本ブリーフサイコセラピー学会の教育講演「マインドフルネス認知療法:注目を集めている理由とその効果機序」において、自転車の乗り方を教えることに例えながら、
“参加者の質問にはマインドフルネスの知識だけでは答えられないものもあります。そのようなときに、自分で実習しているインストラクターであれば、自分がどのように問題を扱うかを示すことができます”3)
と指導者が実践者であることの重要性を示唆しています。
マインドフルネスの語源

マインドフルネスはパーリ語のSati(今ここの経験に気づくこと、今ここを思い出し続け、忘れない心)の英訳として充てられたそうです。「今ここの経験に気づくこと」が注目されて集中力トレーニングのようにみなされていることも多いのですが、前述の伊藤先生によると「今ここの経験に気づくこと」のニュアンスは「周りに人がいることを忘れずに、心配りをしながら」という意味を持っているそうです。
心のモードを変える

書籍「マインドフルネス認知療法 うつを予防する新しいアプローチ」では、マインドフルネストレーニングによって「心のモード」にいつも気づくようになったり、役に立たない心のモードから解放され、役立つ別のモードに切り替えることができるとされています。4)代表的な心のモードは「すること」モードと、「あること」モードです。前提や思い込みに支配されている「すること」モードでいると、なかなか思い通りにならない現実との不一致が心の中で起きてしまいます。この「すること」モードから解放され、「あること」モードに切り替えることができれば、目の前の体験を豊かに感じ取り、自由な選択ができるようになっていきます。
機関紙マインドフルネス研究
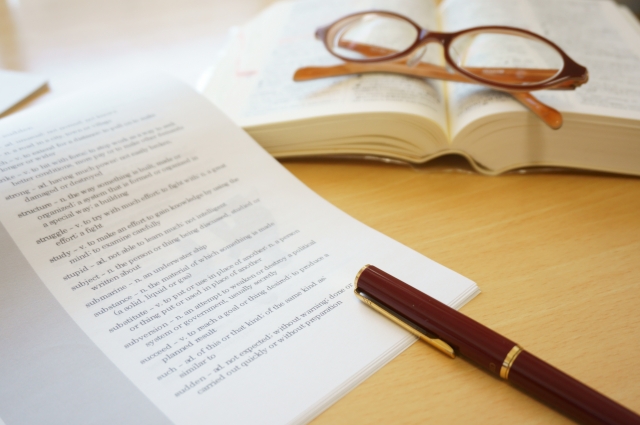
本質を押さえて、素晴らしいマインドフルネスの実践を続けるためには、最新のマインドフルネスに関する情報や科学的知見がとても役に立つと思います。日本マインドフルネス学会の機関紙マインドフルネス研究は「完全にオープン・アクセスの電子ジャーナルとし,誰でも読める利便性を目指します。5)」として誰でも読めるように公開されています。ぜひ、活用してみてください。
日本マインドフルネス学会の機関紙マインドフルネス研究
日本マインドフルネス学会
『参考資料・サイト』
1) マインドフルネス研究 2017年 第2巻 第1号 セルフコンパッションは育てられる
伊藤 義徳(琉球大学法文学部)
2) 日本マインドフルネス学会第3回大会「プログラム・抄録集」
大会⻑挨拶大会⻑ 熊野宏昭(早稲田大学人間科学学術院教授) (日本マインドフルネス学会 副理事⻑)
3)ブリーフサイコセラピー研究 第19巻1号「マインドフルネス認知療法:注目を集めている理由とその効果機序」越川房子
4)マインドフルネス認知療法 うつを予防する新しいアプローチ p40
Z.V.シーガル,J.M.G.ウィリアムズ,J.D.ティーズデール著 越川房子 監訳
5) マインドフルネス研究 2016年 第1巻 第1号巻頭言
日本マインドフルネス学会 編集委員会(杉浦 義典 伊藤 義徳 菅村 玄二)を代表して 杉浦 義典
記事 メンタルヘルスコンディショナー・白石真樹
コメント
この記事へのトラックバックはありません。


























この記事へのコメントはありません。